2025年7月、書籍『ChatGPTで身につけるGoogle Apps Script AIと、目指せプロ級!』(以下、GAS本)が発売されました。ChatGPTを使うことで、Google Apps Script(以下、GAS)の学び方はがらっと変わっているようです。著者であるタカハシノリアキと、編集担当であるマイナビ出版の伊佐さんが、書籍のみどころとともに解説します。
※本記事は、2025年6月28日にVoicyチャンネル「『働く』の価値を上げるスキルアップラジオ」で行われた生放送の内容から制作しています。
初心者のプログラミング学習は、AIを使うのが当たり前に
タカハシ 今回の書籍は、プログラミング学習の初心者向けです。いわば、2024年8月に出した「ChatGPTで身につけるExcel VBA(以下、VBA本)の姉妹本ですね。編集してみてどうでしたか。
伊佐 GAS本は入門書の位置付けですが、読み終わったら「ほぼ一人前」になれる内容に仕上がりましたね! 私は、VBA本ができあがったときから、タカハシさんにGAS版を書いてほしいと思っていました。これまで初心者のプログラミング学習は、書籍やWeb記事を読んでインプットし、1人でコツコツ勉強を進めるのが普通だったと思います。
でも今は、わからないことをAIに聞きながら進められるので、疑問点がすぐに解消できるし、さみしさも感じにくいんですよね。プログラミング学習のやり方ががらっと変わり、新しい時代になったと感じます。VBA本のときは「新しい学習方法が出てきたな」と感じましたが、今ではむしろAIを使うのが当たり前になってきました。
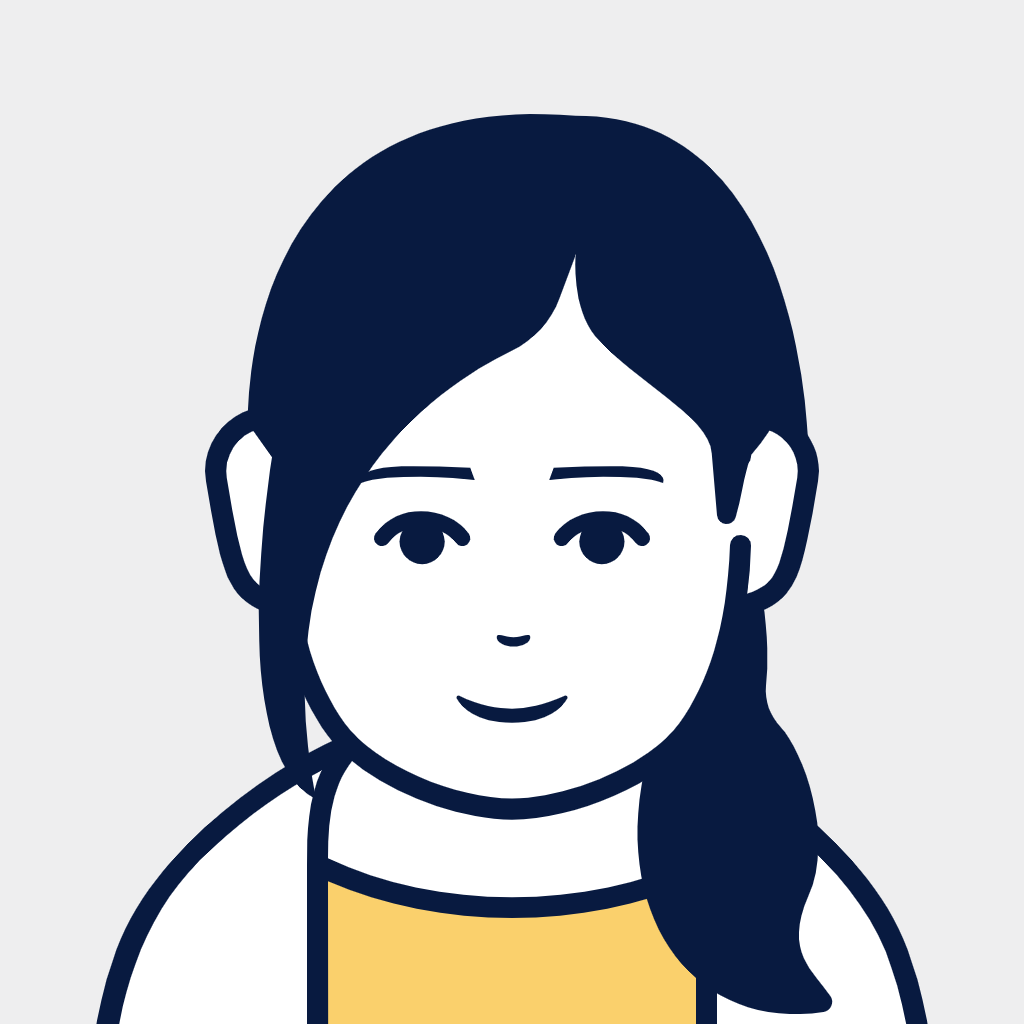
タカハシ VBA本からGAS本まで1年弱空きましたが、その間に、僕たちがAIに向き合うスタンスや受け入れ具合はかなり変わりましたよね。もちろん、AI自体もすごく優秀になりました。
1年前は、AIに難しいことを聞くと回答にハルシネーションが混じることがあったので、プロンプトの調整が必要でした。VBA本の解説には、「この回答が出たらハルシネーションなので気をつけてください」と書きました。でも今回はほとんどありませんでしたね。AIが出した回答を、GAS本にすんなり採用できました。
伊佐 ハルシネーションが全然なく、とにかくスムーズになったことにはびっくりしました。以前は、古い書き方が混ざっていたり、回答のテンションが毎回違ったりしましたよね。AIの精度がどんどん上がっていることを実感します。ほどよく愛嬌ある感じで同じテンションで答えてくれる、1人の仲間に補佐してもらっている感覚でした。
タカハシ 逆に今回やっかいだったのは、ChatGPTの説明が長すぎることです。疑問に端的に回答してほしい人も多いと思うんですが(笑)。「聞いたこと以外のポイントは回答しなくて良い」とプロンプトに入れるなど工夫が必要かもしれません。

伊佐 AIからの回答はかなり長くなりましたね(笑)。でも、箇条書きやリスト表示などを多く使ってくれるので構造的で、読みにくいと感じることはあまりありませんでした。
カスタム指示を入れることでぐっと使いやすくなる
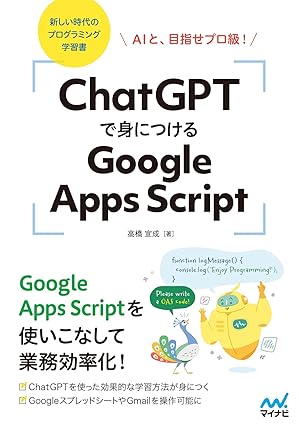
タカハシ ポイントとしては、事前の設定としてChatGPTに「カスタム指示」をしておくと、かなり効果があると思います。カスタム指示は、ChatGPTに「こう説明して」「このコマンドは使わないで」など、自分のルールを指示することです。例えば「中学生でもわかるように」と入れると平易な表現で返事が返ってきます。ある意味、ChatGPTを制御した状態でずっと会話できるのが便利なところですね。
伊佐 ChatGPTの回答があれだけスムーズだったのは、きっと、タカハシさんのカスタム指示やプロンプトが上手だからですよね。「いいプロンプトの書き方」の説明はいろんな媒体で見かけますが、カスタム指示について説明しているのはあまり見ないので、すごく価値のある情報だと思います。GAS本の魅力の1つですね。
タカハシ 最近は「Vibe coding(バイブコーディング)」という概念が流行っています。プログラミングのことをほとんど知らない初心者でも、「こういうツールをつくって」とAIに指示すれば、希望に沿ったものがその場でできあがるという意味です。自然言語で、ふんわりと希望を伝えさえすれば、誰でもシステムやアプリを開発できる。そのメリットはたしかに大きいと思います。
ただ、まったくの初心者がノリでAIに指示するよりも、経験者からの助言や意見を踏まえてつくったほうが、結果的に得られるものが大きいと思います。何かしら手引きがあれば、コーディングの仕組みを理解しやすくなりますから。
伊佐 まだ日本語がうまくない子どものうちから日本語の英訳ばかりやっていると、日本語と英語のどっちつかずになってしまうみたいな話ですね。
初心者が実践レベルまで進み、手応えを得やすい構成
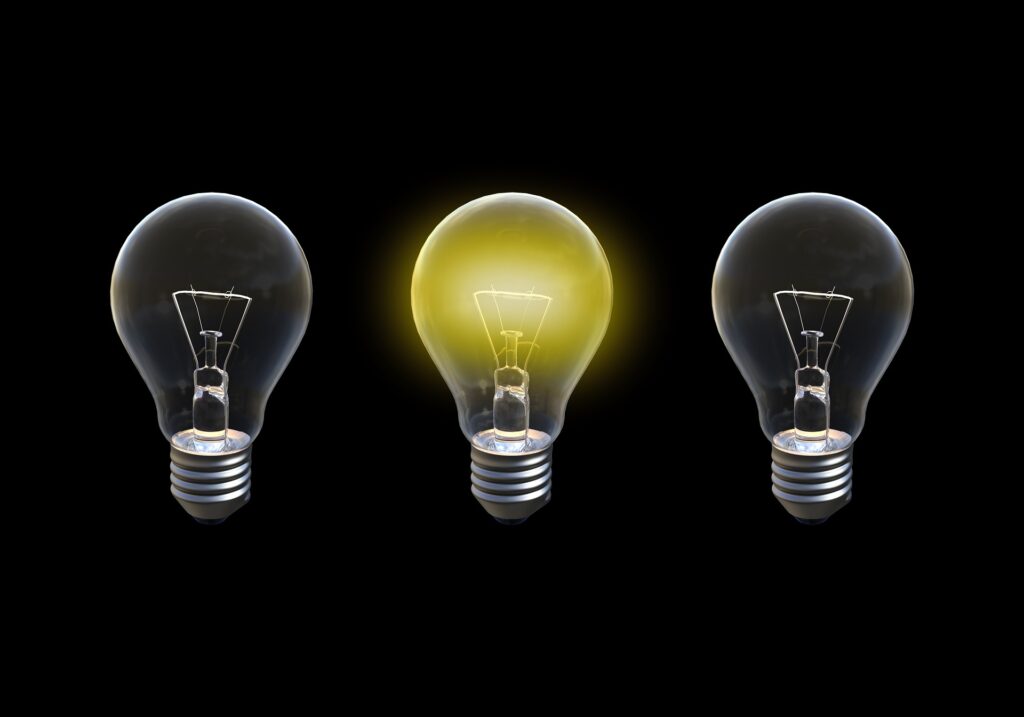
伊佐 GAS本の魅力は、最初の一歩から初心者が手応えを得られる段階まで、かなりコンパクトにまとまっていることです。例えば、1〜7章ではコツコツ文法を学びますが、8章の「スプレッドシートの操作」から9章の「Gmailの操作」、最後の10章「プログラムの開発と保守」では一気に実践モードに入ります。
いざ実践が始まれば、いろんなことができて色とりどりの世界が見えますから、手応えを得られやすいと思います。まったくのGAS初心者でも、自分のやりたいことをほぼ網羅できるんじゃないでしょうか。GASを齧ったことがある人なら、8章から読み始めてもいいくらいです。
タカハシ 7章までに学んだことが、下積みとして生きてくるんですよね。説明では、GASに関連するサービス全体の構造を大事にしています。そこをしっかり学んだからこそ、全体の構造がつながってきて、より理解しやすくなると思います。
伊佐 7章までで学んだことはこれだったのかと、実践しながら腑に落ちる感じがあると思います。一般的に、初心者向けの学習本はハードルの低さを重視するので、難しくなりすぎないよう、「初心者が2,3歩進めるレベル」を目指します。一方でGAS本は、初心者が実践できるレベルまでコンパクトに網羅しているのが特徴だと思います。
タカハシ GAS本のもう一つの特徴は、新しい概念がむやみやたらに登場しないことです。例えば、ChatGPTにコードの解説をもらう際、まずは必ずサンプルコードを渡します。サンプルコードは、その時点で読者に覚えてほしい最低限の概念と、それまでに学んだ内容だけでできているので、初心者もChatGPTの回答を無理なく理解できるからです。
もしここで、まだ習っていない配列やオブジェクトまで全部出てくると、わけがわからなくなると思うんです。僕は解説を書くときいつも、この工夫をしています。
伊佐 VBA本でも、同じ工夫を入れていましたよね。当時「すごい、発明的!」と感じたので、GAS本でも踏襲しました。
AIにはできない「初心者向けの匙加減」

タカハシ 一般的に、初心者向けの書籍はスタンスが2つあるように思います。「簡単にできます!」と全面に押し出すか「ある程度大変だけど、乗り越えたら楽しいよ」と伝えるか。タカハシ流は後者です。前者では、学習し始めてから苦しむ弊害が大きいので。でも最近は、AIのおかげで手軽さを訴えやすくなりました。伊佐さんは、編集の立場から気をつけたポイントはありましたか。
伊佐 全体的にタカハシさん流のやり方に乗った上で、GAS初心者である読者が振り落とされないように、1つひとつの説明の難易度をチェックしました。例えば関数の説明のパートでは、複数のパターンがあると初心者は混乱しかねません。でも、だからといって1パターンの解説だけ載せると、ほかのパターンに出くわしたときに挫折してしまいます。だから、考えうるパターンはちゃんと説明したほうが親切だなと。
タカハシさんにも、解説の中で図を交えたり、わかりやすいように順番を変えたりと工夫していただきました。誰でも、戸惑うことなく読み進められる構成になりましたね。
タカハシ 世の中に出回っているGASのコードは、難しい関数を使っているものが多いし、ChatGPTもそれを学習しているので回答の中にいろんな関数を入れてくるんですよね。読者からすると、その内容を理解できなければ先に進めません。僕がかつてプログラミングの初心者だったころ、書籍で勉強していたときにも似た現象がありました。でも、そこを読み取れるかどうかで差がつくので、ぜひノンプログラマーにも頑張ってもらいたいと思います。
オブジェクトの概念も、GAS本の中にどれだけ入れ込むか悩みました。説明しないことには先に進めないし、その後の理解にもつながってくるので、やはり入れてよかったです。伊佐さんの編集で、「ここだけすごく肝心だよ!」「なんとなくわかっていればOK」という塩梅で濃淡を付け、あまり重たくならないようにしてもらえました。ChatGPTに聞くと、懇切丁寧に全力で説明されるので、きっと初心者には重たいと思うんですよね(笑)。
伊佐 初心者からすれば、新しい概念やキーワードがたくさん出てきますが、「誰にとっても難しいものだ」「だいたい理解できていればOKなんだ」とわかれば、気が楽になります。AIには、そのあたりの匙加減はできませんよね。人が書いたり編集したりする価値は、まさにこういうところにあるなと思います。

