企業や組織のDX・デジタル人材活用・各種事例に関しての調査や研究したレポートや記事をお送りします。
DX
-
 DX
DX
地域の学び場づくりの秘訣とは!?Setouchi-i-Baseデジタルリスキリング実践講座開催レポートその2
香川県高松市にあるオープンイノベーション拠点「Setouchi-i-Base」で、デジタルリスキリング実践講座を担当しました。今回は「地域の学び場づくりの秘訣とは!?Setouchi-i-Baseデジタルリスキリング実践講座開催レポートその2」をお送りします。 -
 DX
DX
目指せ、地域の学び場づくり!Setouchi-i-Baseデジタルリスキリング実践講座開催レポート
香川県Setouchi-i-Baseでのデジタルリスキリング実践講座。デジタルリスキリングに加えて、地域の学習コミュニティづくりをするというおもしろい取り組みでした。今回は「目指せ、地域の学び場づくり!Setouchi-i-Baseデジタルリスキリング実践講座開催レポート」です。 -
 DX
DX
全日本病院学会in京都に参戦して見てきた病院DXの現在地
先日開催された「第65回 全日本病院学会 in 京都」に参加してきました。今日は、なぜ参加したのか、そこで見えてきた病院DXの現在地についてレポートしたいと思います。 -
 DX
DX
DXの成功条件はこの3つ!ホームセンター「GooDay」の事例から学ぶ
先日「データサイエンティスト協会九州支部設立5周年記念セミナー」に参加してきました。今回はそのレポートも兼ねて「DXの成功条件はこの3つ!ホームセンター「GooDay」の事例から学ぶ」と題してデータサイエンスとDXについて考えてきたいと思います。 -
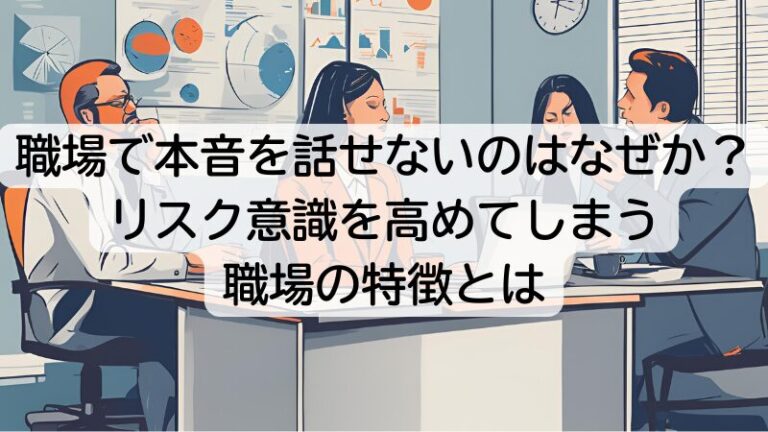 DX
DX
職場で本音を話せないのはなぜか?リスク意識を高めてしまう職場の特徴とは
パーソル総合研究所の「職場での対話に関する定量調査」では、職場で本音で話せているかどうかの実態が示されています。今回は、どうして本音で話せないのか、本音で話せない組織はどのような特徴を持つのか、「職場で本音を話せないのはなぜか?リスク意識を高めてしまう職場の特徴とは」と題して考えていきます。 -
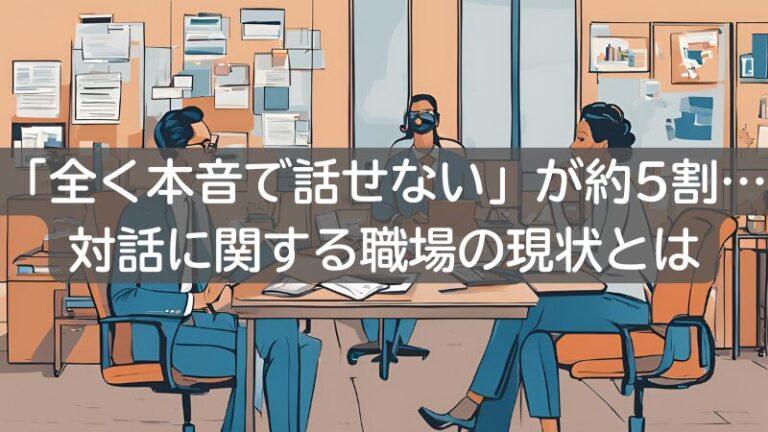 DX
DX
「全く本音で話せない」が約5割…対話に関する職場の現状とは
DXが騒がれている中、少なくない企業は変わることができないという現状に。そのひとつの鍵として注目しているのが「対話」です。今回はパーソル総合研究所の「職場での対話に関する定量調査」からその現状と可能性について考えていきます。 -
 DX
DX
DXするなら「Dの前にX」!九州DX未来会議で語られた5つの成功事例
福岡、佐賀、大分でのDX成功事例を一挙に知り、学ぶことができるイベント「九州DX未来会議」。そちらで5つのDX成功事例についてうかがいましたので詳細レポートしていきます。キーワードはDXするなら「Dの前にX」です! -
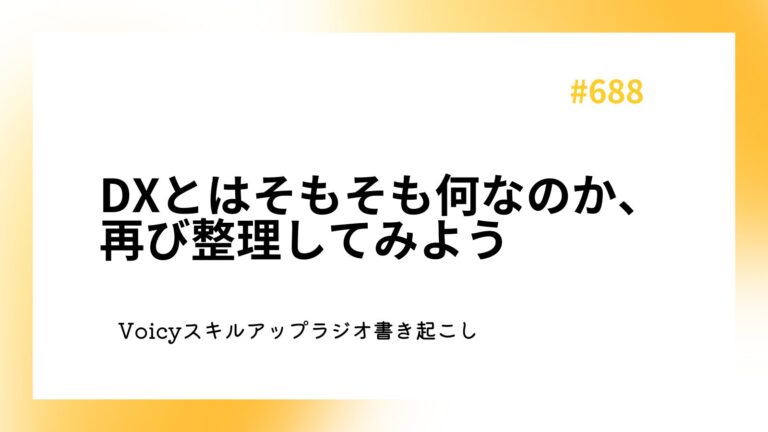 DX
DX
DXとはそもそも何なのか、再び整理してみよう
再び注目が集まるDXについて考えます。企業経営においてDXはもはや避けて通れないものとなっています。しかし、DXに取り組む前には、DXで解決したい課題は何なのか、変化を促すことができるのかなど、しっかり準備する必要があります。 -
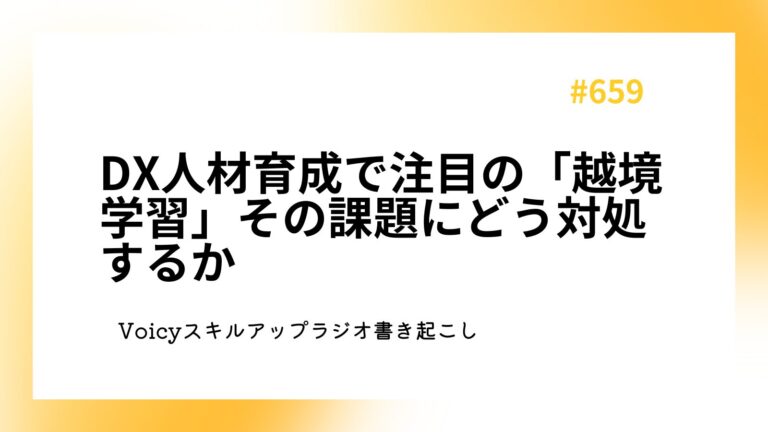 DX
DX
DX人材育成で注目の「越境学習」その課題にどう対処するか
今回は、越境学習の話題についてお伝えしたいと思っています。人材育成には越境学習をすると効果があると言われていますが、越境学習を実際に進める上でいくつかの課題があるということが分かっています。それについて、新たな対処の仕方、素晴らしい考察をされているコラムがありましたので、ぜひ紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 -
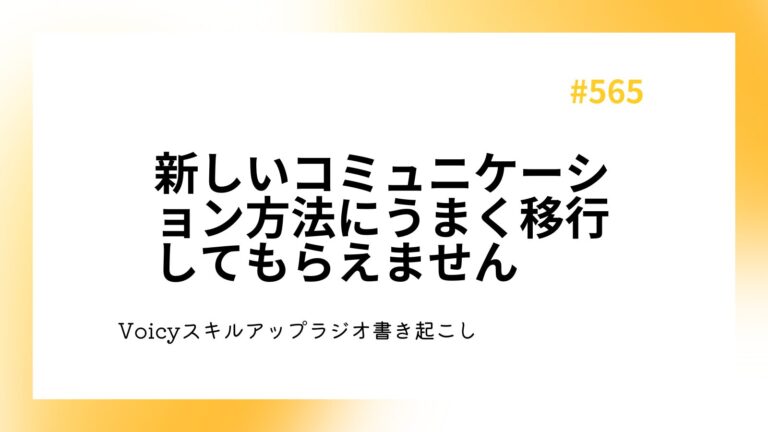 DX
DX
新しいコミュニケーション方法にうまく移行してもらえません
FAXなどの紙ベースからSlackなどの新しいコミュニケーション方法に移行していきたいのに、なかなかうまく移行できない場合、どうすれば状況を打破できるかについて考えます。職場のコミュニケーションを円滑にするための方法についてお伝えします。
