ChatGPTやGemini、Claudeなど、たくさんの生成AIサービスが登場しています。しかし、選択肢が多すぎるゆえに、どれをどう使えばいいのかわからず悩んでいる人が多いよう。その1人であるライター・さくらもえが、学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」(ノンプロ研)の主宰であり、生成AI講座の開発者・講師も務めるタカハシノリアキに、AIを使いこなすポイントを聞きました。
複数のAIを使いこなして、自分にとってベストな使い方を見つけよう
――AIを使って、もっとアウトプットのクオリティを上げたり仕事を効率化したりしたいです。でも、結局どのAIがいちばんいいのか、どれを使えばいいのかわかりません。
多くのAIサービスがあり、どれも精度が高くなってきましたね。僕も、2025年に入ってから意識してAIを使い倒し、自分なりにコツを掴みました。
その中で僕が出した結論は「複数のAIを使い分けるべし」ということです。かつての僕は「ChatGPTがあれば十分」と考えていました。でも、複数のAIを使っているうちに考えがガラッと変わりました。
AIサービスはそれぞれに特徴があり、さらにモデルごとにも得意・不得意があるんです。まずは一通り試してみて、自分の目的達成にいちばん貢献してくれるAIを見つけましょう。用途別に最適なAIが見つかるはずです。やりたいことに応じて最適なツールを選び、その上でプロンプトを工夫するのが、AI活用の近道です。
AIを使う目的や用途は人によって違いますから、1つの正解はありません。「自分に合うものはどれか」を探すため、まずは手を動かして試行錯誤してみましょう。
文章を書いたりブラッシュアップするときは「Gemini」

――タカハシさんは、具体的にどのようにAIを使い分けていますか。
主には、GeminiとChatGPT、Perplexityを使っています。この3つを組み合わせることで、タスクにかかる時間短縮はもちろん、アウトプットの質も上がりました!
Geminiは、ブログ記事を書くときや、文章をブラッシュアップするときに使っています。“僕っぽい”文体やニュアンスを再現するのが得意みたいで、いちばん相性がいいんですよね。例えば、僕は「Voicy」で毎日音声配信をやっていますが、その中身をブログ記事にするとき、Geminiにベースの文章を書いてもらっています。
それを僕が見て適宜直してブログにアップしますが、手直しの量が少しで済むのでとても楽です。昔ChatGPTでやっていたときは、1回あたり約1時間かかっていましたが、今は30分で投稿予約まで完了するようになりました。
Geminiの長所だと思うのは、僕の伝えたいことを削らず、余計な脚色もしないところ。ほかのAIは、まったく意図していない情報を勝手に付け加えたり、ストーリーを捏造したりすることがあったんです。
「Deep Research」機能」はコンサル代わりに使える

コミュニティの方針づくりや会社の経営立案などの高度なリサーチには、Geminiの「Deep Research」機能も使っています。これは、インターネット上にある膨大な情報を集めて、分析し、詳しいレポートを作ってくれる機能です。無料でも使えるのに有料級に精度が高く、かなり優秀だなと感じます。
例えば、僕が主宰している学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」(ノンプロ研)について「会員数を増やすための施策をレポートして」と頼んでみました。Geminiは、既存メンバーの流入元なども参照した上で、かなり正確な仮説を立てて提案してくれたんです。ノンプロ研のことを、誰よりも網羅的かつ客観的に理解しているのはGeminiかもしれません(笑)。
つくづく思うのは、これまで僕がSNSやブログで発信してきた情報がデータになり、こうやってGeminiに分析させることができるのだということです。ネット上にアウトプットし続けていると、それを元に精度の高い現状分析ができるんですよね。発信を続けることの価値が、思いもよらなかったところで出てきたなと感じます。
カスタマイズできるのが便利なChatGPT
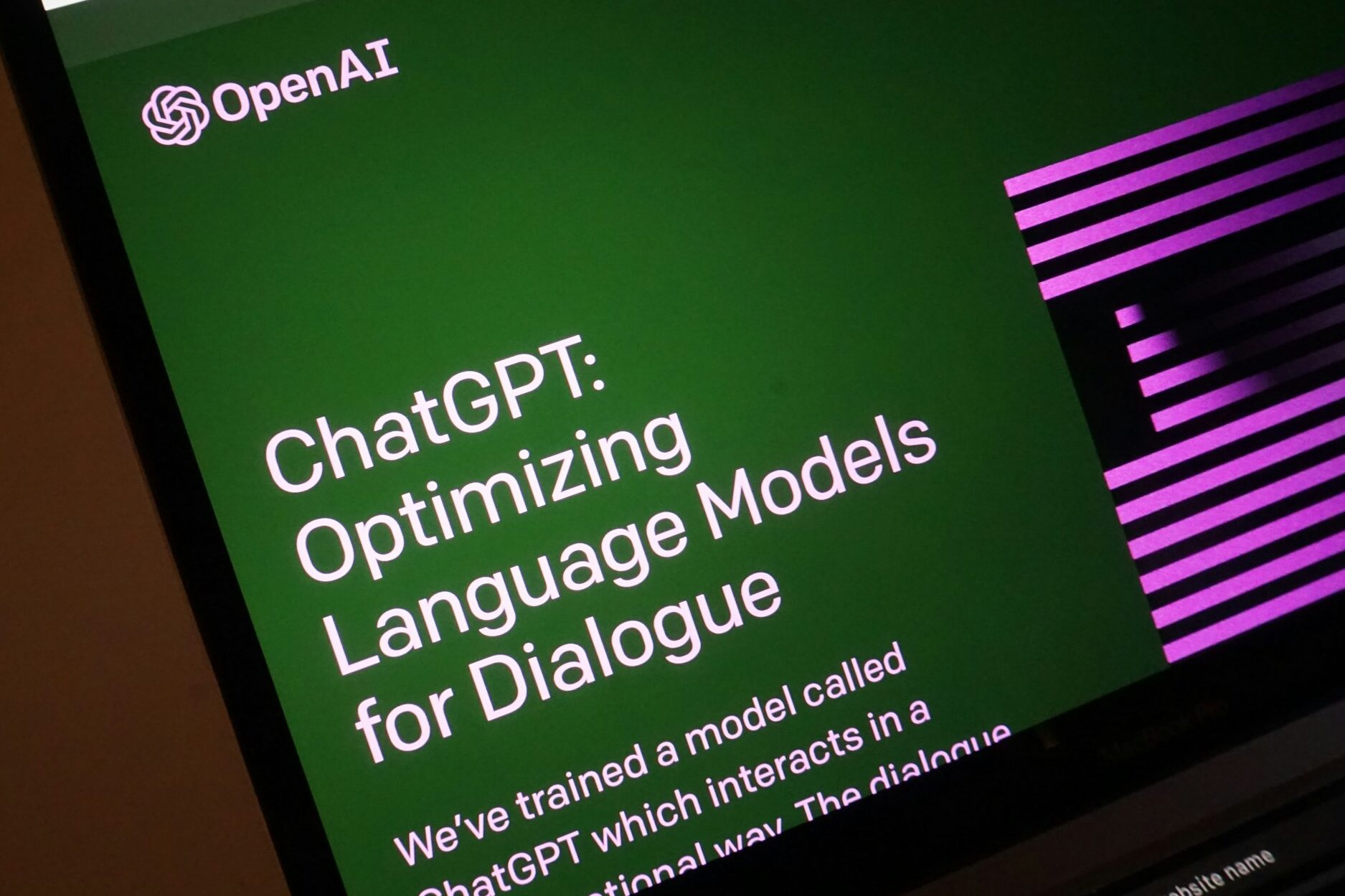
ChatGPTは、定型的な作業や特定のタスクを自動化するのに使っています。オールラウンダーでいろんな機能を一定以上のクオリティで使えるのが、ChatGPTのいいところです。
それから、簡単にカスタムAI(GPTs)をつくれるのも便利ですね。私は『SEOアイキャッチメーカー』というGPTsをつくって、ブログ記事のタイトルへの評価、アイキャッチ画像やパーマリンク、ディスクリプションの作成などを自動化しています。
例えばVoicyの放送内容を文字にしてSEOアイキャッチメーカーに入れると、SEOの観点からタイトルを評価し、点数をつけてくれます。さらに「もっと点数を上げるにはどうしたらいいか」まで考えて、複数の改善策を提案してくれるんですよ。
SEO対策はAIと親和性が高いテーマなのだと思います。ネット上にSEOのノウハウがたくさん転がっていて、各AIがその内容を十分に学習しているので、いい改善策を提案してくれるんですよね。画像やパーマリンクについても相談できるので、僕は大助かりです。
最近面白かったのは、ChatGPTと音声で会話できる「ボイスモード」です。先日、目標設定や優先順位の付け方についてボイスモードでChatGPTに相談し、その様子をVoicyで配信しました。AIと、気軽なおしゃべりを通じてアイデアを深められるのが面白いです。
放送としてじゅうぶん成立する内容になったので、これからも使っていきたいです。台本の準備がいらないし、一発撮りで収録することになるので、準備が最小限で済むのも良いポイントです。最近は、暇なときにAIとおしゃべりしている人もいますよね(笑)。
また、ChatGPTはチャット履歴を記憶して回答に反映させる「メモリ機能」も大幅に強化されました。今後は、よりパーソナライゼーションが進みそうです。
信頼性の高い情報を集めるならPerplexity

Perplexityは、検索に特化したAIです。その時点での最新の情報を取ってこられるのが強みですね。また、検索ソースを学術論文など信頼度の高いものに限定できる機能があり、リサーチや情報収集に重宝します。
僕は、Voicyの台本作成にPerplexityを活用しています。僕のブログでは、毎週金曜日に「週刊Work&Techニュース」という企画をやっていて。その1週間にあったワークとテックに関するニュースを5本紹介し、さらに同じ内容をVoicyで配信するというものです。僕が5本のニュースをピックアップし、そのタイトルをPerplexityに渡します。そうするとPerplexityがタイトルをもとにインターネット上を検索し、Voicyの台本を仕上げてくれるんです。
Perplexityは、よく使うプロンプトを登録しておける「Spaces」機能があって便利です。僕は台本作成のプロンプトを登録しているので、それを入れれば、ほぼそのまま使える台本が出来上がるようになっています。そうしてつくった台本をベースに、僕が感想を入れたり微調整をしたりして、配信に進みます。台本をGeminiに渡せば、ブログの文章もできます。
僕は毎日Voicyとブログで配信をしていますが、去年までは、その台本作りや収録、記事化にかなりの時間がかかっていたんです。配信とブログ記事の作成に2.5時間くらいかかっていて、ほかの仕事に割くリソースが圧迫されてました。AIを使ってこの時間を圧縮しようと僕なりに研究した結果、2.5時間かかっていたものを1.5時間くらいに短縮でき、しかもクオリティが上がったというわけです。
無料版でもOK?課金すべき?コストに関する考え方

――ほとんどのAIは無料でも使えますが、有料プランにすればいろいろな制限がなくなり、より使いやすいと聞きます。AIに「課金」するかどうか、どんな基準で検討すればいいでしょうか。
たしかにどの生成AIでも、無料プランには、利用回数や機能に制限がある場合が多いです。有料プランでは、最新モデルを先行して使えるメリットもあります。でも、最初から課金する必要はありません。
試行錯誤の末「このAIが自分の作業にベストだ!」と見つけたが、無料の範囲では作業が成り立たない……という状況になったら、そのとき課金を検討すれば十分です。少し前に有料プランでリリースされた機能が無料プランに降りてくることもたびたびあるので、それを待つ選択肢もありますよ。
新しい生成AIがどんどん生まれ、各社が激しい競争を繰り広げています。その一環で、比較的安価で多機能なプランを提供する動きも見られます。
例えばGeminiは、月額2,900円で、かなり高性能かつ高機能なサービス「Gemini Advanced」を展開しています。Googleが、潤沢な資金力を背景に、本気で競争に参加してきた感があります。ちなみに「Gemini Advanced」は、法人向けGoogle Workspaceに契約していれば使用可能です。
ーーAIを使うポイントは、手を動かして、複数のツールを比べてみることだとわかりました。実践的な使い方で試してみたいと思います!
そうですね。AI活用で成果を出す鍵は、「1つのツールに固執せず、複数のAIの特性を理解し、目的に合わせて柔軟に使い分けること」。まずは、質を上げたい、効率化したいと思う特定の作業に対して、複数のAIを試してみましょう。そのうち、それぞれのツールの得意なこと、苦手なことが感覚的に掴めてくるはずです。

