プログラミング学習は、初心者にとってとても壁が高く、挫折しやすいといわれます。それが今、ChatGPTの力で変わってきました。Google Apps Script(以下、GAS)の学習やAIを取り巻くトレンドについて、2025年7月にマイナビ出版から発売された書籍『ChatGPTで身につけるGoogle Apps Script AIと、目指せプロ級!』(以下、GAS本)を通し、著者であるタカハシノリアキと、編集担当である伊佐さんの対談で探ります。
※本記事は、2025年6月28日にVoicyチャンネル「『働く』の価値を上げるスキルアップラジオ」で行われた生放送の内容から制作しています。
トップのエンジニアと、AIに代替されるエンジニアに分かれる
伊佐 書店でプログラミング本が並んでいる棚を見ると、並んでいる本の方向性がどんどん変わっていくなあと思います。最近はAI関連のコーナーが広がっていたり、LLMの書籍がたくさん並んでいたりと、発見がありますよね。
タカハシ AI関連の書籍は本当に増えましたね。実際、トップクラスのエンジニアはどんどん市場価値が上がって高単価になっています。そもそもシステムを設計したり、さらにその前段階で顧客のニーズを見極めて企画を立てたりできる人は、どんどん評価を上げています。逆に、指定されたコードを書くことしかできないと、AIに代替されて仕事がなくなっていくんじゃないでしょうか。
日本では、システムを設計する人とコードを書く人が別々なことが多いです。そうなると、コードを書く部分は、設計する人がAIに指示して書いてもらってもいいという判断になりかねません。今はだんだんとその危機感が大きくなっているからか、エンジニア界隈がざわついています。
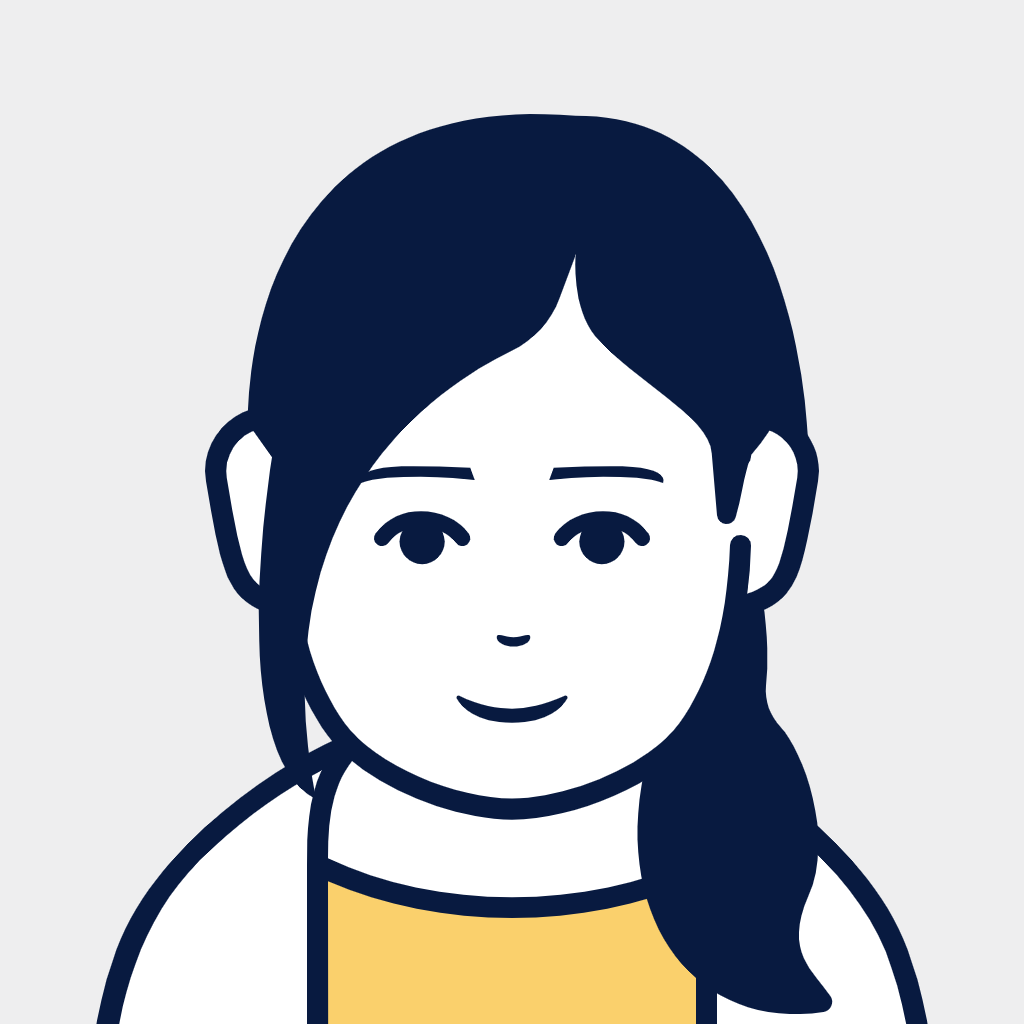
伊佐 自社の業務内容をどうシステムに落とし込んでいくのか、そもそもどこに問題があってどの部分をシステム化すべきか線引きするのはかなり難易度が高いです。AIには判断がつかない部分もあると思います。
人間には「コードを読む力」「文脈を限定する力」が試されている
伊佐 もう1つ、レビュー力、つまり「読む力」が試されるようになったように感じます。コードはAIに指示すればそれなりにいいものができあがりますが、それに対してレビューは必須です。単なるコードの動きだけではなくて、ほかの部分と整合性がとれているか、変更しやすい仕様かなども考える必要があります。また、AIがやりがちな落とし穴があれば、それを見つけられるのは人間です。

タカハシ プログラミングは無限に広がりがちな言語空間なので、だからこそ人間の力が問われますね。もう一つは「限定する力」も大事です。文脈や背景(コンテキスト)の情報を正しく与えると、AIはそれに沿って出力してくれます。つまり人間側には、「どうやって正確な文脈をAIに渡すか」が大事。話の範囲を正しく狭めることで、よりよいアウトプットをもらえます。
例えば変数を知りたいとき、ChatGPTにサンプルコードを渡すことで、解説が発散しないで済みます。「このコードの解説をして」と依頼すれば、ChatGPTからの回答に余計な情報が入りづらいんですね。サンプルコードを入れずに「変数を教えて」と質問してしまうと、いろんな変数を使ったサンプルコードが山ほど提案されてしまい、話が散らかります。
文脈を限定する技術は、プログラミング以外でも使えます。僕は長年ブログを書き続けているので、「この内容で、タカハシノリアキっぽい文章を出して」とAIに指示すると、僕っぽいものをちゃんと出してくれるんです。例えばブログの構成案をつくって、「これに沿ってブログ記事を書いて」と指示すると、的確なものを数千文字程度書いてくれます。クオリティはかなり高いです。
プログラミングの基礎知識があれば“無双”できる世界になってきた
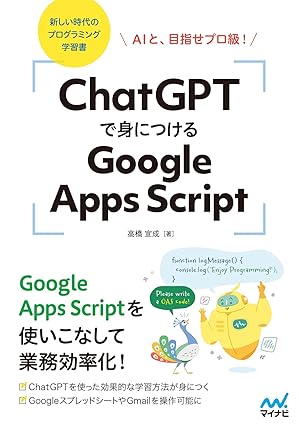
伊佐 生成AI関連は次から次にトピックが出てくるので、読者のみなさんもつねに新しいものを追いかけているように見えます。それにつれて、プログラミング学習のトレンドもどんどん激しく変化するようになりました。だからなおさら、「ChatGPTでプログラミング言語を学ぶ」という切り口を変えずに続けていくことに価値があると思います。
大事なのは、発信するタイミングですね。遅すぎると旬を逃してしまうし、逆に早すぎると読者も様子見をしてしまいます。トレンドの変化が早いから「1カ月後には変わるでしょ」と思われてしまうんですね。
タカハシ 1カ月後の流行りがどうなっているかは誰にもわかりませんね。最近の流行りとして、伊佐さんがキャッチしている情報はありますか?
伊佐 今は「Claude Code」がホットですね。みんな新しいAIエディタに注目して、課金して試しているようです。これまでのAIエディタはVisual Studio Codeに機能を追加して使うのが王道でしたが、最近のものはCommand Line Interface (CLI)で操作するようになりました。本職のエンジニアが使う“ガチ勢のツール”という雰囲気が、ノンプログラマーにも刺さるのかもしれません。
タカハシ とくにGeminiのCLIはホットですね。アウトプットとしては、例えばGoogle スプレッドシートにトリガーを入れておいて、メールが届いた際に自動でGmailの下書きを生成している人がいました。このレベルなら初心者でもすぐにつくれますし、実用的でちょうどいいですよね。
伊佐 生成AIのおかげで、プログラミングの入り口がだいぶ広くなってきた感じがします。AIに質問すればぴったりのコードを書いてくれるし、日常業務や普段の生活でも使えそうです。おもしろいし便利だけど、なんだかちょっと怖い世界になってきましたね。
タカハシ そうですね。ある程度プログラミングの知識を持っていれば“無双”できる世界になってきました。自分1人で抱えきれるようなサイズのシステムなら、基礎的な知識があれば完成させられると思います。もちろんプログラミングの知識だけでなく、AIに対するリテラシーや判断基準も必須ですね。例えば、外部に漏れたらまずい情報とそうでないものを見極める力も必要です。
コミュニティで学ぶと、その効果の高さがわかる

伊佐 タカハシさんはご執筆のほかにも、コミュニティの運営やイベントなどにも注力されています。今とくに興味のある分野はありますか?
タカハシ これからは、「コミュニティづくりがうまくいく方法」を言語化していきたいと思っています。例えばノンプロ研のようなコミュニティで学ぶ行為にどんな意義があるのか、どうすれば運営がうまくいくのか。ノンプロ研はとてもうまくいっていますが、その理由を言語化しないと再現性がないように思うので。技術ドリブンではなく「広く、みんなに学んでもらうためにはどうしたらいいか?」が僕の興味関心の中心にあります。
今のプログラミング学習は、初心者でも1人でコツコツ頑張るのがスタンダードになっていて、誰かと一緒に学ぶ選択肢が少ないように思います。それが、学びが苦しくなる理由の一つでもあるんじゃないかなと。ノンプロ研で仲間と学べば、その学習効果の高さがわかります。プロのエンジニアだって、会社に属していれば、スキルを伸ばせるように育成プログラムが組まれるはずです。それと同じ営みをノンプログラマーにも応用すれば、みんな楽しく効率よく学べると思います。
伊佐 何かうまい学習方法のネーミングがあれば、ノンプログラマーの方々も「あ、それ知りたかった!」と興味が湧いてくるかもしれません。よく、IT企業のチーム運営手法をビジネスフィールドに転用するテクニックがありますが、それと同じで、フックさえあれば多くの方に刺さるんじゃないでしょうか。ビジネスでもプライベートでも、潜在的にプログラミング学習の情報を求めている人は多そうです。
情報が溢れているからこそ「どう切り取るか」に意味がある

伊佐 学習コミュニティの主宰や音声配信などいろいろな活動をされているタカハシさん。書籍やブログの執筆活動にはどんな意義を感じていらっしゃいますか?
タカハシ ものを書いて人に伝える営みは、僕の中ですごく大事です。コミュニティやイベントで人と触れ合う機会ももちろん貴重ですが、それとは違った価値があるんですよね。かつて僕がGASを勉強し始めたころ、Googleの公式ドキュメント(英語版)に加えて、日本のエンジニアがブログに書いてくれていた解説を参考にしていたんです。僕も、それをノンプログラマーにもわかりやすい情報にして発信したいと思うようになり、ブログを始めました。
最近は、「ほしい情報があるときはAIに聞けばいい」という風潮があります。手軽さやスピードはAIが圧倒的なので、文章を書くモチベーションが下がっている人もいると思います。でもAIはあくまでも、過去に書かれたテキストや、すでにある情報の中からしか回答を出せません。ものを生み出したり、新しい一歩を踏み出したりする部分は人間の力が必須なので、その役割を担っていけたらと思っています。
時代とともに求められる情報の中身は変わりますが、書いて残す行為は必ず必要だと思います。僕も、プログラミングに限らず、その営みの中に参加していたいなと思っています。
伊佐 そのうち、著者の方から「書籍を書くことにどれだけ意味があるの?」とかな、と言われる日もくるのではないかと思っています。でも私は、情報が大量に溢れているからこそ「どう切り取るか」に意味があると思っています。そこに価値を感じてくれる著者さんと一緒に、いい書籍をつくっていきたいです。

