みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
今年もありがたいことに、東京工芸大学大学院の集中講義で教鞭を執らせていただきました。
生成AIが当たり前になった今、学生たちの学び方や課題、そして僕が感じた彼らの持つ無限の可能性についてお話しします。
ということで、今回は「3年目の大学院集中講義で感じた「生成AI時代」の学びの変化と学生たちの可能性」についてお伝えします。
では、行ってみましょう!
3年目の夏、東京工芸大学での濃密な5日間
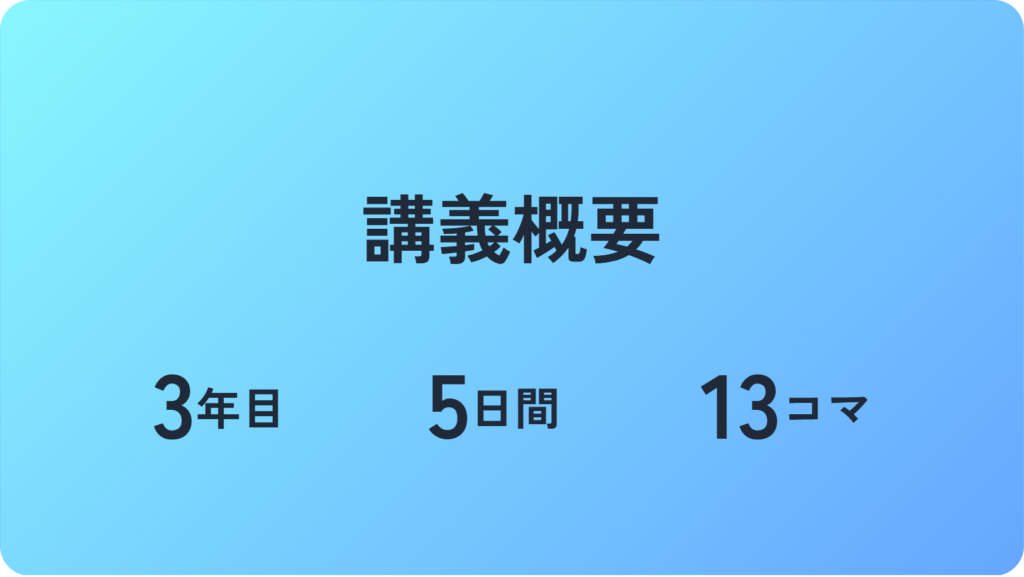
僕にとって夏の恒例行事となりつつある、東京工芸大学大学院での集中講義「ビジネスコンピューティング特論」の非常勤講師。
今年で無事に3年目を迎えることができました。8月4日から8月8日までの5日間、神奈川県の厚木市に滞在し、学生たちと向き合う日々です。
1コマ110分という授業を合計13コマ。
文字だけ見ると「うーん、結構長いなぁ」なんて思われるかもしれませんが、これが始まってみると本当にあっという間なんです。
毎年、学生たちの熱意と真剣な眼差しに触れることで、僕自身も多くの刺激をもらい、濃密な時間は瞬く間に過ぎていきます。
デジタル時代の必須スキルと「学びのしんどさ」の正体
この講義のベースとなっているのは、僕の著書である『デジタルリスキリング入門』です。講義の大きな目標は2つあります。
なぜ今、デジタルリスキリングが必要なのか
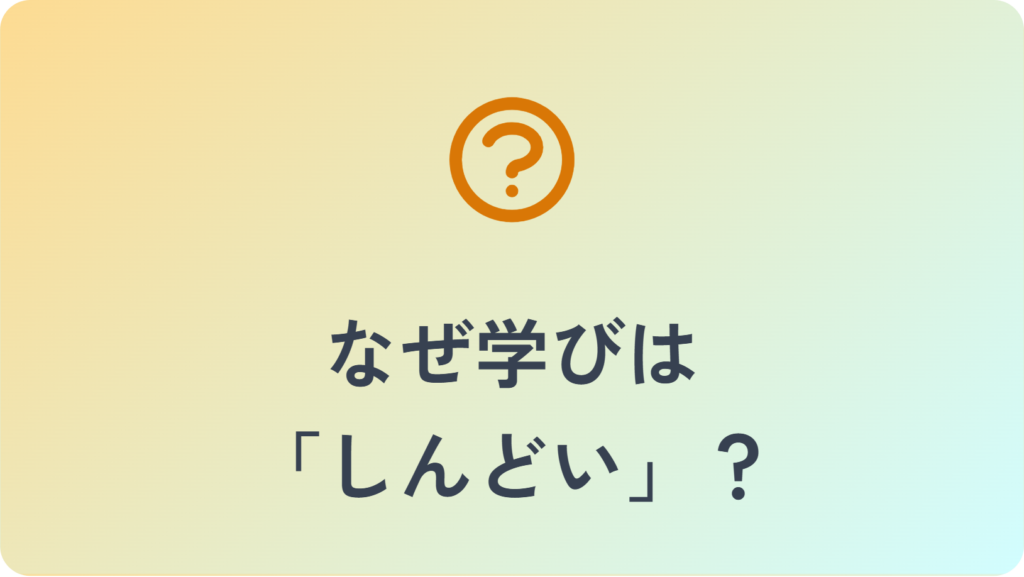
まず一つ目の目標は、「ビジネスパーソンがデジタルスキルを身につける必要性と課題について理解し、説明できること」です。
インターネットが登場し、スマートフォンが普及し、そして今、AIが社会のあり方を根底から変えようとしています。
次々と起こるデジタル関連のイノベーションは、私たちの働き方や暮らしに大きな影響を与えていますよね。
こんな時代にあって、「ITは苦手なんで…」と目を背けていては、これからの社会で活躍するのは難しいでしょう。教育者として、そんな無責任なことは口が裂けても言えません。
しかし、頭ではわかっていても、実際に新しいデジタルスキルを学ぶのは「しんどい」と感じる方が多いのも事実です。
では、なぜ学ぶのはしんどいのか?そして、どうすればそのしんどさを乗り越え、楽しく学び続けることができるのか?
講義の1回目のイントロダクションでは、まずその点についてじっくりとレクチャーします。
さらに、11回目、12回目では現在の日本のソフトウェア開発の現場や、多くの企業が課題として挙げるDX(デジタルトランスフォーメーション)のリアルな現状についても触れ、なぜ今、私たちが変わらなければならないのかを伝えていきます。
「しんどい」を乗り越えるための戦略とロードマップ
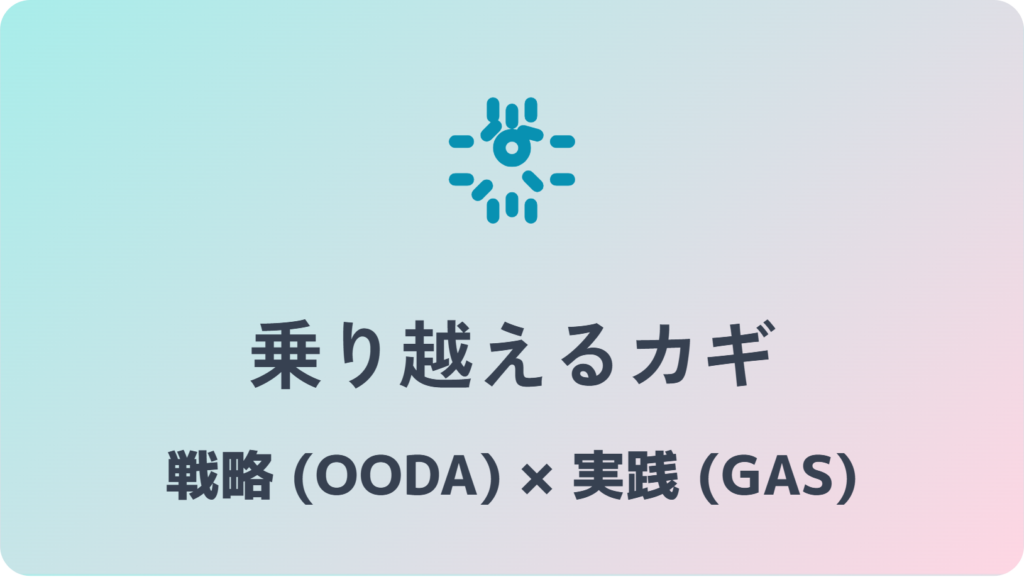
そして二つ目の目標が、「デジタルリスキリングの戦略とロードマップを理解し、実行に移せるようになること」です。
ただ闇雲に勉強を始めても、途中で挫折してしまうのが関の山です。そこで重要になるのが「戦略」です。
講義では、第2回目から第4回目にかけて、状況に応じて柔軟に計画を見直す「OODAループ」という考え方をベースに、学習を継続するための「5つの原則」(学習の原則、環境づくりの原則、実践の原則)を学びます。
そして、第5回目以降は具体的な「ロードマップ」として、まずは日々の業務効率を上げるための時間管理術から始め、デジタルスキルの全体像を掴みます。
そこから、データ活用の基本であるスプレッドシート関数、さらにはプログラミングの第一歩としてGoogle Apps Script(GAS)といった、実践的なスキル習得の入口まで学生たちを案内します。
最終日の成果発表で見えた「生成AI時代」の課題
講義の最終日には、学生一人ひとりが5分間のLT(ライトニングトーク)形式で成果を発表します。この5日間で何を学び、これからどう活かしていきたいのか。僕にとって、この成果発表が一番の楽しみでもあります。
そして今年、3回目にして、時代の大きな変化を肌で感じることになりました。
情報収集の先にある「自分の言葉」の価値
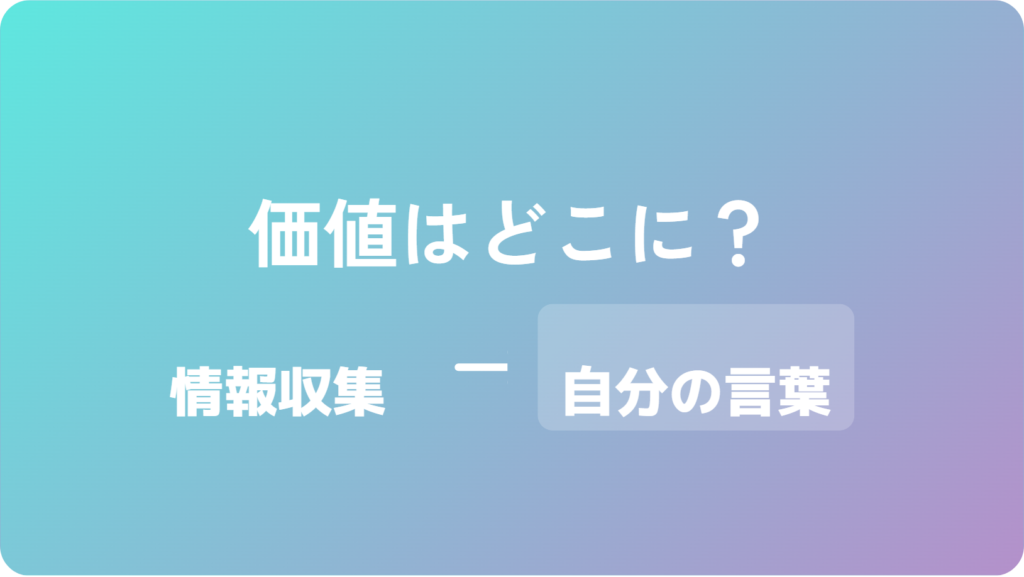
もちろん講義の中では、「生成AIに丸投げしただけの発表はダメですよ」と釘を刺していました。そのおかげか、あからさまにAIが書いたような発表は一つもありませんでした。
しかし、どうにも気になってしまったのが、「情報収集」で終わってしまっている発表が多かったことです。僕の肌感覚では、発表時間の半分くらいがそうだったかもしれません。
例えば、「自らの研究領域におけるAIの活用事例」や「今後注目すべきスキルについて」、「特定のツールの紹介とその活用技術」といった内容です。
発表内容自体はよくまとまっているのですが、そこに「あなた自身の考え」や「これからの行動」が結びついていないように感じられました。
これは、僕自身の中に「その情報、AIに聞けば数秒で集められるよね」という強力なセンサーが育ってしまったからかもしれません。
情報そのものの価値が相対的に下がり、その情報をどう解釈し、自らの経験や想いと結びつけ、未来の行動に繋げていくのか、という部分にこそ価値が宿る時代になったのだと痛感しました。
発表を聞きながら、「5分間という貴重な時間の中で、君自身の想いはどこにあるんだろう?」と、少しもどかしい気持ちになったのも事実です。
質問を投げかけることで見えてきた学生たちの個性
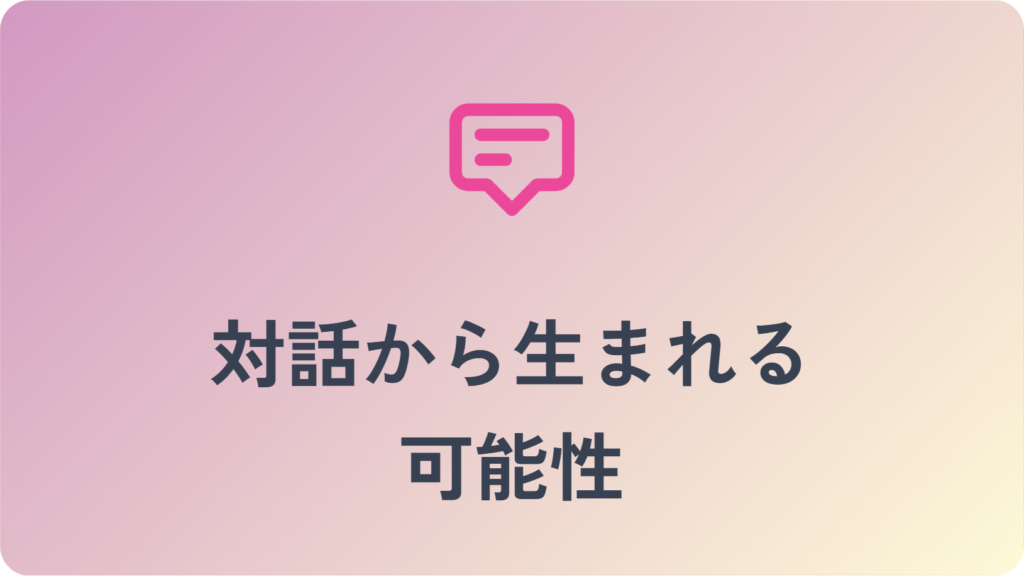
でも、ここで終わらせません。
プレゼンテーションが終わった後、僕は必ず全員に何かしらの質問を投げかけるようにしています。
すると、発表だけでは見えなかった彼ら、彼女らの「自分らしい言葉」が、そこではじめて返ってくるのです。
その言葉たちは、たどたどしいながらも、それぞれの思いや感情が含まれており、それぞれの良さが出ていました。
なんだ、みんなちゃんと考えているじゃないか。やればできる。
ただ、その一歩を踏み出す機会が少なかったり、自分の考えを表現することに慣れていなかったりするだけなんだな、と気づかされました。
一人ひとりに個別に関心を示し、対話の機会を設けてあげること、そしてこのような発表の場でもそれをしていいよと伝えること、その重要性を改めて感じた瞬間でした。
高等教育でAIをどう学ぶべきか、そして今後
AIをどう学び、どう付き合っていくべきか。この問いについては、僕自身もまだ考え続けている途中です。
今回の講義を通して、また新たな気づきや思うところがたくさんありました。これについては、また別の機会にじっくりとお話しさせてください。
毎年、学生たちから多くのことを学ばせてもらっています。
彼らがこれからのデジタル社会でたくましく、そして自分らしく活躍していくための手助けが少しでもできたなら、教育者としてこれ以上の喜びはありません。来年もまた、この場所で彼らに会えることを楽しみにしています。
まとめ
以上、「3年目の大学院集中講義で感じた「生成AI時代」の学びの変化と学生たちの可能性」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

