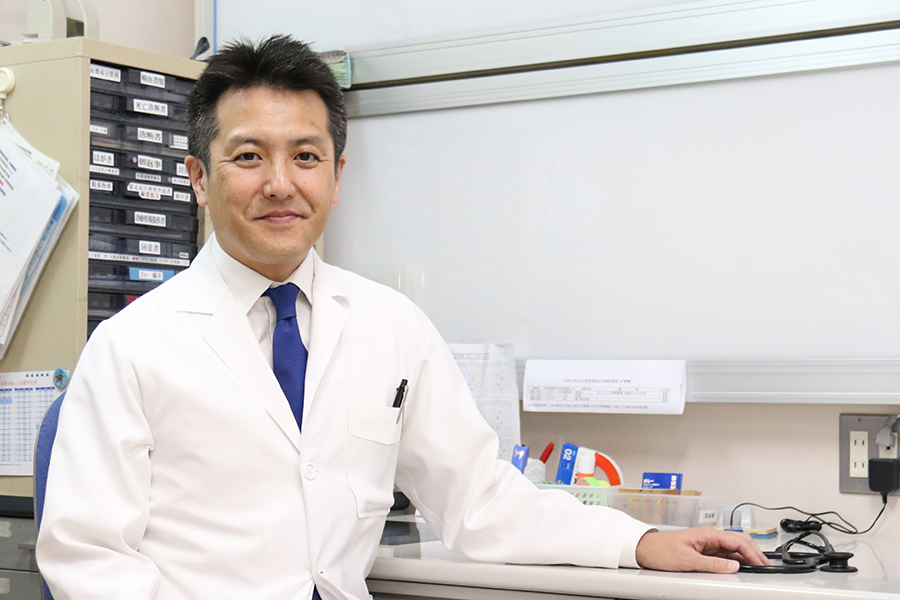165床のベッドを持ち、慢性期疾患や回復期を扱っている福岡県北九州市の新栄会病院。現場の第一線で働くメンバー2人が、ノンプロ研の「越境学習プロジェクト」に参加しました。院長の永田雅治さんに、プロジェクトを終えた今感じている手応えについて伺いました。
医療DXが進んでいないことに、強い危機感があった
――今回、越境学習プロジェクトに参加することになったきっかけを教えてください。
きっかけは、以前からお付き合いのある山口征啓先生に紹介してもらったからです。山口先生とは日常的にお付き合いがあるほか、生成AIに関する講師をしていただいた経験もあります。その山口先生からの紹介とあって、最初から安心感がありました。
2023年8月ごろに電子カルテを導入したことを受け、院内で「DX(Digital Transformation)を進めていこう」「デジタル人材を育てよう」という空気が出ていたときに、山口先生からお話をいただきました。具体的なプロダクトのプランはありませんでしたが、面白そうなのでとりあえず乗ってみようと思いました。
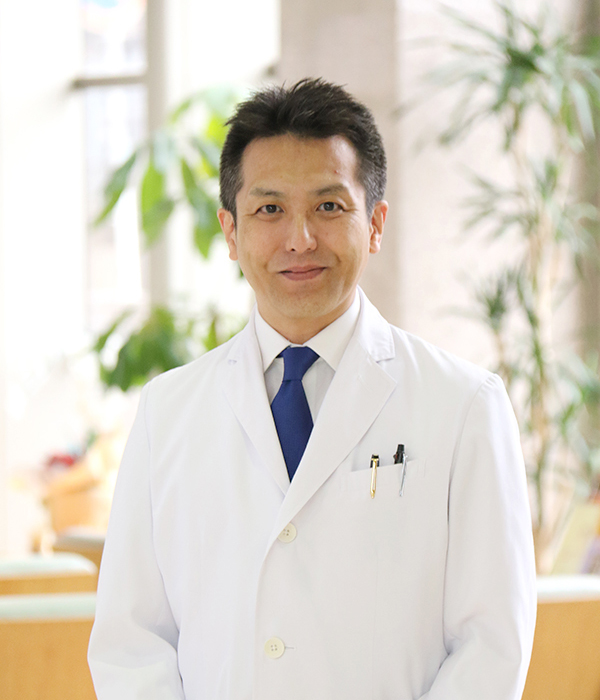
永田 雅治さん
越境学習プロジェクトに参加した組織の事例には、埼玉県のイムス富士見総合病院や、当院と同じ北九州市の小倉第一病院があります。小倉第一病院はご近所なので、ある程度状況もわかります。同じように成果を出せるなら、当院もやってみたいと率直に思いました。
――医療DXに対する危機感があったのでしょうか。
はい。危機感は今でもあります。私たちの社会福祉法人小倉新栄会は、グループとして新栄会病院を含め全8つの施設を抱えています。デイサービスやケアハウスから保育園まで幅広いのですが、施設間をつなぐデジタルツールはまだありません。医療現場では電子カルテを使えますが、介護や保育の現場では使えません。
でも、この状態を問題視する人はほとんどいませんでした。昔と同じやり方で困ることはなかったし、デジタル化することのメリットもわかっていなかったからです。紙で管理している情報をデータ化すれば作業が楽になったり、情報共有が早くなったりするということを知らないから、昔と同じやり方で満足していたのだと思います。
私自身、DXにはいつか手を付けないといけないと思っていました。でも、それを当院で働くメンバー全員に理解してもらうのは現実的ではありません。まずはデジタルに明るい人や組織の中で権限を持っている人が始めて、後についてきてもらうしかないので、そういうメンバーを数名、ノンプロ研に送り出そうと思いました。
第一弾として参加希望者に挙手を求めたところ、三木さんが手を挙げてくれました。また平山さんは入院患者のデータを扱う仕事をしているので、プログラミングと相性がいいと思い、声をかけました。
2人が気を遣わなくて済むように、あえて直属の上司を介さずに進めました。また経済的な負担はかけたくなかったので、業務扱いにしました。代わりに2人には、最終的に何かしらのツールをアウトプットしてもらうよう依頼しました。
参加者の2人を孤立させないように、トップメッセージを発信
――越境学習プロジェクトに参加することについて、どうお感じになりましたか。
正直、越境学習とは何なのか、具体的にどんなことをやるのか全然わかりませんでした(笑)。なので、学びの内容や過程を間近で見たいと思い、私自身が「伴走者」の役を担うことにしたんです。
最初は、越境学習にあたってなぜ伴走者が必要なのか疑問でしたが、話を聞いているうちに、参加者の様子を客観的に観察することに意味があるのだなと気づきました。学習の中身を知り、理解するのに加えて、「こういうこともできるんじゃないか」と未来のビジョンを描けます。それは経営者として必要な要素だと思いました。

――三木様・平山様に伴走する中で、工夫したことはありますか。
いちばんに考えたのは、第1期に参加してくれた2人を院内で孤立させないことでした。2人をねぎらう狙いもあって、当院の全メンバーに向けて、ことあるごとに越境学習について話しました。私の立場からたびたびメッセージを出すことで、2人のモチベーションにもなるかなと。なにより、第1期で終わらせず第2期も続けていきたいと考えていましたから、まずは2人にモチベーション高く取り組んで成功してもらいたかったんです。
伴走者としては、「2人がやっていることを邪魔しないように」という点を第一に考えました。進捗確認は、プロジェクトの途中で開催される「中間発表」に参加する程度。あくまでも、ホーム(職場)側の環境を整えて、安心して越境学習できるようにするのが自分のミッションだと思いました。
新栄会病院のように慢性期疾患を扱う病院は、一般的に中途採用が多く、職員の年齢層が高めといわれます。各自が自分のキャリアの中で培ってきたスキルや価値観があり、いい意味で多様性のある環境です。一方、全員に共通するベースが薄いので、新しいことを始めるときは苦労することもあります。
だからこそ、越境学習が周りからもポジティブに受け止められるよう、院内の空気づくりの面で配慮しました。
予想以上にすばらしい成果が出た
――2024年末に、1期が終了しました。三木さんと平山さんの成果について、どう捉えていらっしゃいますか。

2人とも、私の予想以上にすばらしいものをつくってくれました。2人が共同でつくった、GAS(Google Apps Script)とVBA(Visual Basic for Applications)を使った入退院患者一覧表は本当に便利そうだなと思います。リスキリングの意味でも、とても大きな成果を出せました。
また、三木さんはノンプロ研に残って、講座のTA(ティーチング・アシスタント)に挑戦しています。できれば今後もっとたくさんのチャレンジをして、三木さんのキャリアとして伸ばしていってほしいなと思います。
プロジェクトの最後には、学習した成果を発表する「LT(ライトニングトーク)大会」が開かれます。2人の発表を聞いて、コツコツ積み重ねてきてくれたんだなとよくわかりました。自主的に勉強したからこそ、このアウトプットを出せたのだろうなと。また、ノンプロ研側の講師やTAの方にも、客観的な立場からていねいに面倒を見てもらえているなと思いました。
参加者2人はすばらしい成長を遂げましたが、院内の他のメンバーは、まだ「プログラミングを使ってどんなことができるかわからない」という状況です。実際に現場にある悩みをプログラミングで解決していけば、越境学習の輪が広がっていくんじゃないかなと思います。そうして、越境学習やデジタル化、DXがすばらしいことであるという空気感をつくっていきたいです。
優秀な人材をつなぎとめる手段として、リスキリングの後押しを
――スキルアップだけでなく、お二人のキャリアにもプラスに働きますね。
今、医療や介護業界は、かなり経営が厳しい状況です。法定価格で診療報酬や介護報酬が決まっているので、どんなにレベルの高い治療やケアを提供しても、料金は全国均一。賃上げの時代に逆行している業界だと思います。
つまり収益を伸ばしようがないし、人件費を増やすことも難しい。しかも、その中でも無資格の事務系職種の給与は低めに設定されています。病院の屋台骨を支えてくれているのは、事務方のメンバーなのですが……。
私としては、現場のスタッフは本当に頑張ってくれていますから、やりがいだけではなく給与面でもっと恵まれてほしいし、職場を好きになって働いてほしいです。病院が人件費を増やすのは難しくても、リスキリングの支援はできます。そうして得たスキルや知識、人脈を、副業として外部で発揮してもらえたらいいんじゃないかと。そうすれば、結果的に病院でも長く勤め続けてくれると思うんです。
経営の視点からも、転職が一般的になってきた世の中で優秀な人材をつなぎ止めるには、副業をうまく使うしかないと思っています。例えばプログラミングなどのIT系なら、リモートで働けるので、本業と両立させやすいでしょう。そうしてスキルを磨けば、いずれはよその病院でコンサルタントとして業務委託を受けることもできるかもしれません。院内で周りから頼りにされるだけでは、モチベーションは長く続きませんから、そういう活躍の場が必要ですよね。
とくに看護師や栄養士などは、資格を持っている分、離職のハードルが比較的低いといわれます。いかに「働きつづけてもらうか」は経営者として大事なテーマです。その手段の一つとして、ノンプロ研を活用できたらと思っています。
異業種のメンバーと接する経験は、大きな財産になる

――ノンプロ研というコミュニティに対して、どんな感想をお持ちですか。
今回は第1期として、「ひとまず越境学習を始めてみた」という状況でした。その中でいちばんの学びは、外部のコミュニティに越境して、異業種の方と接する経験自体が大きな財産になるということです。他業種の方々と意見交換するのも貴重な経験でした。
医療業界は専門性が高い分、どうしても仲間内で固まってしまい、視野が狭くなりがちです。自発的に外部のコミュニティに越境していかないと、外の世界を全然知らないまま「今のままでいいんだ」と思ってしまいます。医療DXに悩んでいる病院は多いはずなので、こんなに良い学習方法があるんだと知ってもらいたいです。コストパフォーマンスの面でも、とても優位性の高い学習方法だと思います。
また、講師やTAをはじめノンプロ研メンバーの方々のスキルの高さや積極性、意欲の強さ、雰囲気のよさには驚かされました。みなさんそれぞれ業務をこなしながら、プログラミングについてもプロ並みの知識を持っています。しかも、わからないことを質問すればいつでも噛み砕いて教えてくれるんですよね。おかげで、越境学習にはどんな学びがあり、参加者がどういうふうに伸びていくのか、よくわかりました。ぜひこれからもお付き合いしていきたいです。
ノンプロ研に入って初めて、世の中にはデジタルやプログラミング、DXのプロがこんなにたくさんいるんだと知りました。デジタル化について外部の企業に依頼すると、業務で活用するイメージを持ってもらうのが難しく、提案の引き出しが少ないように感じます。
でもノンプロ研にはいろんな職種の方がいるうえ、プロ並みの知識を持っている方々に教わることができます。だからこそ、日常業務に活かせる実践的な方法を考えられます。プロの選手ではなく、部活の先輩に教わって上達していくようなイメージですね。
医療の現場でも、今やデジタルはインフラの一つ
――これからも、越境学習を続けていきますか?
はい、ぜひ2期以降も続けていきたいです。院内でも「1期で終わらないよね」という空気があります。現在は、参加者を募集しているところです。いかんせん年齢層の高い職場なので、とくに若いメンバーにはチャレンジの後押しをしようと思っています。
ノンプロ研の越境学習プロジェクトでは、毎週ちゃんと宿題を出してもらえるし、質問にもていねいに答えてもらえるから続けやすいんですよね。結果的に、投資額以上の成果を得られます。
アウトプットによるコスト削減効果までは明確に測れていませんが、それよりも今は、組織として種まきをする時期だと思います。院内に、デジタル化を進めるカルチャーを醸成していけるように、メンバーを増やしていきたいです。医療の現場でも、今やデジタルは必須のインフラです。三木さんや平山さんにばかり仕事が偏ってしまわないよう、デジタルがわかる人を増やして、各部署にまんべんなく配置できたらと思っています。
――越境学習プロジェクトをきっかけに、医療DXが進んでいきますね。DXについて、今後の展望を教えてください。
足元では、グループの施設間で、患者さんのデータを横串で見られるシステムをつくりたいです。それには数年かかると思いますが、将来的にはケアレベルを上げたり、マーケティングに使ったりできたらと思っています。
今はどの病院も、何をしたらいいか、どんな取り組みなら効果が出るのかわからず模索している状況だと思います。1つわかっているのは、DXを進めないと、働き手が減っていく状況では経営を維持できなくなるということ。経営者はみんな悶々としていると思います。
どこまでいっても、DXを前に進めるのは人です。デジタルのスキルや知識を持つメンバーを育て、適切に配置すれば、少しずつでもDXを進めていけると思います。
とくに介護施設やデイサービスでは、利用者の数に対してスタッフの数は非常に少ないのが現状です。スタッフの年齢層が高いケースも多く、デジタルの基礎知識がないこともよくあります。だから、当院のような、グループの中心的な組織が優先してDXを進め、人を育てていかないといけません。そうやって、きっかけをつくっていけたらと思っています。